2025年2月、東洋水産の「マルちゃん 赤いきつねうどん」のアニメCMが、SNS上で大きな議論を巻き起こしました。このCMをめぐる騒動は、現代の広告表現と視聴者心理の複雑な関係を浮き彫りにしています。
本記事では、生成AIの分析を通じて、この騒動の真相と視聴者の心理を探ります。

CMの概要と炎上の経緯
2025年2月6日、東洋水産の公式Xアカウントが投稿した約30秒のアニメCMが、騒動の発端となりました。このCMでは、若い女性キャラクターが夜のリビングでテレビを見ながら「赤いきつね」を食べる様子が描かれています。
しかし、このCMに対して以下のような批判が相次ぎました。
- 女性キャラクターの表情が「性的」であるという指摘
- 制作過程で生成AIが使用されているのではないかという疑惑
これらの批判は急速に拡散し、SNS上で大きな論争を引き起こしました。
生成AIによる分析
生成AIを使用して、このCMの表現と視聴者の反応を分析した結果、以下のような興味深い洞察が得られました。
1. 表現の両義性
AIの分析によると、CMの表現には意図的な両義性が含まれている可能性があります。女性キャラクターの頬を赤らめた表情は、「おいしさへの感動」と「性的な含意」の両方に解釈できる微妙なバランスで描かれています。この両義性が、視聴者の解釈を分かつ要因となっています。
2. 文化的コンテキスト
日本のアニメ文化において、キャラクターの感情表現を誇張することは一般的です。しかし、グローバル化が進む現代では、こうした表現が文化的背景の異なる視聴者に誤解を与える可能性があることが、AI分析から明らかになりました。
3. 視聴者の投影
AIの分析によると、CMへの反応は視聴者自身の経験や価値観を強く反映しています。「性的」と感じる視聴者は、自身の過去の経験や社会的な文脈をCMに投影している可能性が高いことが示唆されました。
制作側の対応
騒動が拡大する中、2025年2月21日、CMの企画を担当したチョコレイト社と制作を担当したNERD社が声明を発表しました。
弊社企画の「赤いきつねうどん」ショートアニメ広告に関して pic.twitter.com/oZL1gWOzRG
— CHOCOLATE Inc. (@inc_CHOCOLATE) February 21, 2025
「赤いきつねうどん」ショートアニメ広告に関して pic.twitter.com/X4AX9khjE0
— Masaki (@Masaki_NERD_) February 21, 2025
両社は以下の点を強調しました。
- CMの制作過程で生成AIは一切使用していない
- すべての表現はプロのアニメーター・クリエイターによる手作業で制作された
- 表現内容はクライアントと緻密な協議を重ねた上で決定された
また、関係者個人に対する誹謗中傷や虚偽の情報拡散を控えるよう呼びかけました。
視聴者心理の分析
生成AIの分析により、この騒動における視聴者の心理には以下のような要因が影響していることが明らかになりました。
1. 解釈の多様性
同じCMを見ても、視聴者によって全く異なる解釈が生まれる現象が観察されました。これは、個人の経験や価値観、文化的背景の違いが大きく影響しています。
2. SNSの増幅効果
SNS上での議論は、特定の解釈や意見を急速に増幅させる傾向があります。これにより、少数の意見が大きな影響力を持つ現象が生じています。
3. AI技術への不安
生成AIの急速な発展により、一部の視聴者はAIが制作に関与しているのではないかという疑念を抱きやすくなっています。これは、技術の進歩に対する不安や懸念の表れと言えるでしょう。
4. ジェンダーの視点
「Male Gaze(男性的まなざし)」の概念に基づく批判が見られました。これは、広告表現におけるジェンダーの扱いに対する社会の敏感さを反映しています。
今後の広告制作への示唆
この騒動から、今後の広告制作において以下のような点に注意を払う必要があることが示唆されます。
- 多様な視点からの検証:制作過程で多様な背景を持つ人々の意見を取り入れ、潜在的な誤解を防ぐ。
- 透明性の確保:制作プロセスの透明性を高め、疑念を招かないよう努める。
- 文化的コンテキストの考慮:グローバルな視点から表現の適切性を検討する。
- AI技術の適切な活用:AIを使用する場合は、その旨を明確に開示し、人間の創造性との適切なバランスを取る。

まとめ
「赤いきつね」CMの騒動は、現代の広告表現と視聴者心理の複雑な関係を浮き彫りにしました。生成AIによる分析は、この騒動の背景にある多層的な要因を明らかにし、今後の広告制作に貴重な示唆を与えています。
広告制作者は、多様な解釈の可能性を常に意識し、透明性の高いプロセスで制作を行うことが求められます。同時に、視聴者も自身の解釈が唯一絶対のものではないことを認識し、多様な視点を受け入れる姿勢が重要です。
この事例は、生成AI時代における広告表現の在り方と、メディアリテラシーの重要性を再考する貴重な機会となりました。今後も、技術の進化と社会の変化に応じて、広告表現と視聴者の関係も進化し続けるでしょう。
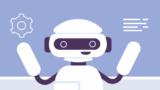
コメント